行政書士は、費用が、弁護士に比べ安めです。ただ、行政書士でも費用が高額(目安として30万円以上)になる場合、事実関係が複雑であるとか高度な法律的検討が必要な場合ですから、弁護士に依頼するべきです。
紛争予防として
価値創造に向けて
契約書の作成・チェック
契約書は、紛争予防の第一歩。例えば、自宅を売却するという場合、売買契約書を仲介業者任せにする。丁寧に見ると細かなところで売手不利な文言があったりします。 契約後、それに気づいても、もう手遅れです。騙されたとは思わなくてもスッキリはしません。契約書の文言を正確に理解し、納得して契約すること、それが紛争の芽を摘むことになります。
民法は、ここ数年、重要な法原理を変更するような改正をしています。従前の感覚が通用しないのです。改正後の民法を理解する必要があります。また、個人情報保護法など民法以外の法令なども、その趣旨を理解し、契約書に落とし込むこが必要な場合も多くあります。 さらに特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)や下請代金支払遅延等防止法(下請法)など押さえておくべき法律も増加しています。
ここ数年、契約を取り巻く法律は複雑化・精緻化しているといえます。またカスタマーハラスメントなど契約関係者の言動が社会問題化する可能性もあります。 適正な契約書を作成しておけば、相手方との問題も契約書に基づいて解決できます。

よくある質問
当事務所に一度ご相談ください。お話を聞き、内容を判断して、必要なら経験豊富な弁護士を紹介いたします。そのように行政書士をお使いください。
売りたい商品、受託する業務、それらの対価など、契約の中心になるものわかるもの、また、どのような手順で処理されていくのか などを、一先ずご教示ください。 また、相手方と決定している事項や、契約書に入れておきたいことなどもあればご教示ください。 リーガルチェックの場合は、契約書を見せていただければと思います。
もちろんです。あなたにとって契約内容が不利になっていないか、法律的に間違っていないか、確認しておくべきです。少し費用は かかりますが、契約に関連する不安を払拭し、将来紛争にしないために納得して契約するようにしてください。
公正証書作成
公証人が行う公証事務で利用者が増加しているのは、遺言公正証書、任意後見契約、信託契約だとされています。また、近年、その重要度が増していると思われる公正証書として離婚給付等契約公正証書があります。養育費や面会交流など子育てに関する重要な事項にかかる合意を離婚に先立ち公正証書にする選択肢もあります。 このほか、借地権設定契約、賃貸借契約に関する公正証書、信託契約・自己信託に関する公正証書、金銭消費貸借、債務承認弁済、売買、贈与、死因贈与、委任、担保設定など各種契約に関する公正証書があります。
以上を一般的に公証制度というのですが、この制度も紛争予防を目的とするものです。公正証書の作成は、最終的に当事者と公証人が公正証書原本に署名押印してするのですが、そこに至るまでにいくつかの手順を踏む必要があります。 特に公正証書の案文点検は重要です。これらを行政書士としてサポートいたします。
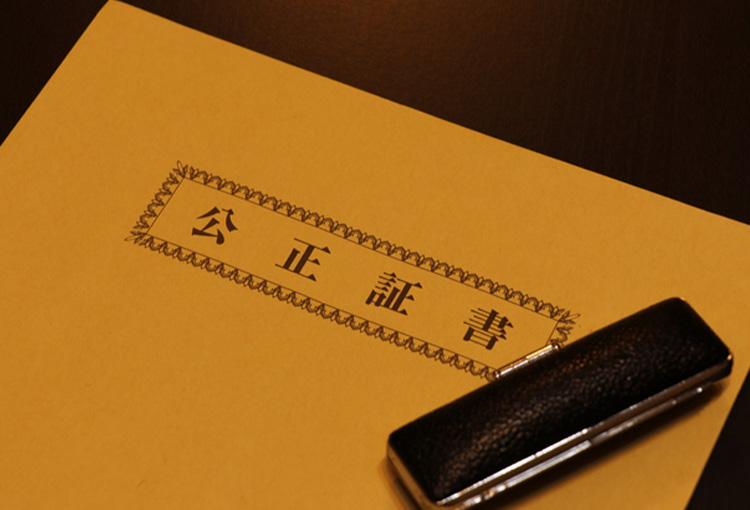
よくある質問
行政書士は、公正証書の作成に必要な書類の準備、公証役場との連絡、嘱託代理(公証役場への出張・手続きの代行)など、公正証書作成をサポートします。
契約書、遺言書、任意後見契約、離婚協議書など、様々な種類の公正証書作成を依頼できます。不動産を伴う場合は司法書士、それ以 外の場合は行政書士が対応することが多いです。
公正証書作成にかかる費用は、公証役場の手数料と、行政書士への報酬によって異なります。報酬は、作成する公正証書の種類や内容 等によって異なります。
公正証書の内容について不明な点がある場合は、公証役場ではなく、弁護士や行政書士に相談しましょう。また、公正証書作成を依頼 する際は、複数の専門家に見積もりを依頼し、費用やサービス内容を比較検討することが重要です。
遺言・遺産分割協議書
遺言書は、父母の、父母が生涯かけて成した財産について、子や孫のことを思ってする最後のメッセージです。また、遺産分割協議書は、父母が生涯をかけて残した財産について、兄弟姉妹によって処分について話し合った結果です。いうなれば、父母から子へと受け継がれる財産を中心とした家族の歴史を記録したものとも言えます。
ただこの局面で兄弟姉妹間の複雑な感情に起因して、厳しい紛争に発展することもなくはありません。
全ての家族が平穏ななかで故人を偲び、悲しみを癒してもらったらと願っています。行政書士として、相続が紛争に至らないよう、遺言書・遺産分割協議書作成に全力で取り組みます。
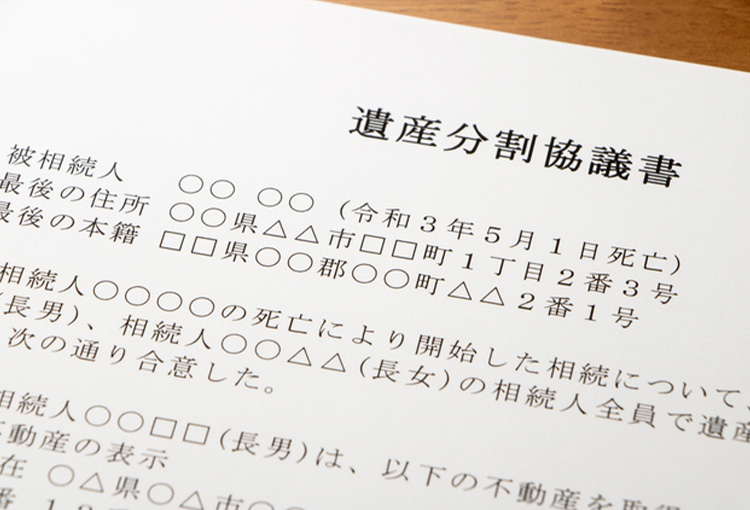
よくある質問
相続財産の有無、多寡というよりも、兄弟姉妹間で紛争にいたる可能性がないなら、敢えて遺産分割協議書を作成する必要もないと思います。ただ、預貯金が複数ある場合は、あえて遺産分割協議書を作成しておくと解約時、効率的かと思います。
AI技術が発達したインターネットで「遺言について」と検索すれば、わかりやすく解説してくれます。ただ、それで理解できない場合や正確な理解に不安がある場合は、弁護士や行政書士に聞くのがいいと思います。 民法は、三種類の遺言を設けていますが、共通するルールとそれぞれのルールを定めています。弁護士、行政書士からその違い、メリット・デメリットを聞くことをお勧めします。
定款作成・補助金申請
会社を設立したり補助金を申請したりする際に、最も重要で最も作成困難な書類が「事業計画書」です。事業計画書とは事業の内容、市場規模、対市場戦略、収益の見込みなどを記載したものです。この良し悪しで金融機関の融資、投資家の投資、そして補助金の採択決定や交付決定が決まります。定款の絶対的記載事項(会社法27条)である会社の目的も、この事業計画書に記載した事業内容にそって定めることになります。起業や事業拡大にあたり最も悩まれるところかと思います。この点、お悩みに寄り添い支援させていただきます。
また、定款作成のほか会社設立や補助金申請は、法律上であるか否かにかかわらず、いろいろな取り決めや手順を履践する必要があります。これらについて、行政書士として代理できるところは代理などして、当初の目的を達成することにご助力いたします。

よくある質問
行政書士報酬の相場は、定款作成から会社設立まで依頼すると、25万円程度が目安になります。さらに定款認証手数料や登録免許税 などが別途かかります。
依頼する際に、旧姓の併記の希望をお申し出いただければ対応いたします。
PDF形式で作成し、電子署名を施して公証人の認証を受ける定款のことです。株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の 収入印紙を貼付しなければなりません。電子定款の場合は不要になります。ただしこの場合も他の手数料は当然かかります(資本金に よって変わりますが、最大目安は6万円強でしょうか)。他に電子定款のメリットとしては、すべてオンライン、webで完結することで す。そのため、書面定款に比べて所要日時も短縮できる場合が多いです。
補助金は課税対象です。所得税、法人税として申告する必要があります。その他、必要な書類、準備する事項などは、多岐にわたります。
事業承継
事業承継については、中小企業を維持発展せるための取り組みであって親族内承継、社内承継、M&Aによる承継があるなどの説明がされています。ただ、例えば、印鑑を彫る技術。近年、公的機関の印鑑省略、あるいは各種申請の電子化によって、印鑑の需要が減少していると聞きます。これらは技術革新や発展による社会の変化によるものとも言えますが、反面では、我が国において奈良時代以降公印として使われ江戸時代には庶民にも広がり、明治以降は制度にまでなった印鑑を彫る技術、つまりは伝統的な工芸技術が消え去ることを意味しています。 それでも印鑑作成の事業を承継など、現状では容易に言えるものではありません。
ただ、このまま日本の伝統的な技術が消え去ることを黙過することもできません。 そうなると、どうすべきか。新たに国内外の需要を喚起する事業を立案し、そのうえで次世代に技術を承継させる手立てを講じるしかありません。
地場産業として各地で伝統的技術をお持ちで、だけど承継のあてなく技術を消滅させるしかないと悩んでおられるようであれば、どうかご相談下さい。 ともに考えていきましょう。ともかく悩んでいる場合ではありません。断行するのみです。

よくある質問
物事を進めていけば、税理士、弁護士などの専門家に相談しなければならない場面に出会うはずです。ただ、承継すべき事業の維持を最初に考えるなら、市場の推移を見極めるところから始めるべきです。手法として市場調査というものも視野に入れるなら、行政書士の事実調査として、取り掛かることも可能かと思います。ともかく、手をこまねいて決めかねていらっしゃるなら、手遅れになってもつまらないので、まずはご相談を下さい。承継を進めるか進めないか、そこからご一緒に頭を使わせていただきます。
各種許認可申請
各種許認可申請こそ行政書士たるべき職責です。 会社設立や事業拡大をする場合にも、国や地方公共団体などの行政機関から許可や認可を得ておくべき場合があります。
以下のものが代表的なものですが、ご自身が起業や事業拡大を考える事業が許認可の必要なものか不明の場合は、一度ご連絡ください。 因みに許認可が必要な事業の代表例は次のとおりです。
飲食店 建設業 運送業 不動産業 医療機関 介護事業 風俗営業 古物商 人材派遣業 廃棄物処理業
ほかに酒類販売許可などというものもあります。

大使館(領事)認証
例えば、海外で婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入などの手続きを行う場合に、日本の公文書を提出するには、大使館認証(領事認証)が必要になります。
また、提出先の国がハーグ条約に加盟している場合、アポスティーユという簡略化された認証で済む場合もあります。
手続きとしては、まず、日本の外務省が公文書に押された公印が本物であることを確認する公印確認を受け、その後、提出先国の駐日大使館または領事館において、外務省の公印確認済みの文書に提出先国の領事認証を受けます。
これで終了ですが、手間暇がかかる手続きでもあります。
以上は公文書の場合ですが、私文書でも可能な場合がありますが、公証役場での公証という手順が加わり、手間が増えたりします。
いずれも申請であって、行政書士であるかぎり委任状なく代理申請することができます。
一度ご相談ください。

